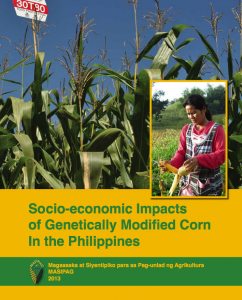カテゴリー: レポート(その他)
その他
フィリピンの遺伝子組み換えによる被害をインドネシア農民に伝える
フィリピンで遺伝子組み換えトウモロコシが導入された後、農民がどう影響を受けたか、調査に基づき作られたドキュメンタリー『10年の失敗—GMコーンに騙された農民たち』に日本語版を作成し、先日公開しましたが、インドネシアで活動するATINA(オルター・トレード・インドネシア)やオルター・トレード・ジャパンの姉妹団体APLAに関わるボランティアの方に翻訳いただき、インドネシア語版が登場しました。
以下にそのインドネシア語版を掲載します。
もしインドネシアの友人をお持ちでしたら、ぜひご紹介いただければ幸いです。インドネシア語版のリンク(YouTube)。日本語版はこちら
インドネシアへのモンサントの進出
モンサントは遺伝子組み換え種子を商業栽培を米国で始めてほどない時期にインドネシアでも遺伝子組み換えコットンを承認させるための活動を始めています。遺伝子組み換え種子を環境審査なしに承認させるために1997年から2002年にわたり、インドネシア政府高官140人以上の役人とその家族に賄賂を贈ったことが暴露され、またその間に無理矢理始めたBt綿(虫が食べると死んでしまうBt毒素を作り出すように遺伝子組み換えされた綿)の栽培も干ばつや害虫の被害が出て、農民との争いとなり、2003年12月にモンサントは一時、インドネシアから撤退します。
しかし、その後、再び、インドネシアに戻り、現在は2つの種子工場を稼働させ、1万トンのハイブリッド種子を生産し、その30%はタイやベトナムに輸出されています。
さらにモンサントはインドネシアからフィリピンに遺伝子組み換えトウモロコシの種子を輸出する計画を持っていると報じられています。ベトナムが遺伝子組み換えの大規模商業栽培が始まる可能性もあり、そうなってしまえばインドネシアが東南アジアの遺伝子組み換え種子工場の拠点になってしまうことが懸念されます。
今年、本格的な遺伝子組み換え商業栽培が始まる可能性
モンサントばかりでなく、インドネシア企業によって、干ばつに耐性のあるとする遺伝子組み換えサトウキビが開発され、インドネシア政府は世界に先駆けてその栽培をすでに承認しており、インドネシアで本格的な遺伝子組み換え栽培が今年2014年に着手される可能性があります。
また遺伝子組み換えトウモロコシの栽培も今年2014年から始まるという情報があります。遺伝子組み換えの本格的な栽培により、フィリピンの農民に起きたことがインドネシアの農民に起きる可能性が高まっています。
こうした現状を考える時、インドネシアでフィリピンの経験を伝えていくことは大きな意味があると考えます。姉妹団体のNGO、APLAと連携しながら、こうしたアジアの農民の経験を共有していきます。
フィリピン:遺伝子組み換えと闘う農民たちもぜひご覧ください。
- 『遺伝子組み換え食品の真実』 アンディ・リーズ著/白井和宏氏訳(白水社)の181〜184ページ。
モンサントがインドネシアに入り込み、わいろで環境調査をパスして、Btコットンの栽培を始め、大失敗して撤退した経緯が書かれています。 - Monsanto Business Practice in Indonesia http://www.monsanto.com/newsviews/pages/business-practices-in-indonesia.aspx
モンサント社自身によるインドネシア賄賂事件の自己批判文書。日本モンサント株式会社のサイトでは見つけることができません。 - How Monsanto brought GM to Indonesia http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2005/9630-how-monsanto-brought-gm-to-indonesia-1012005
GMWatch(遺伝子組み換え問題に関わる代表的NGO)によるインドネシアへ2001年Btコットンが持ち込まれた時の状況を説明した記事(2005年) - 2013/05/18 Monsanto eyes RI’s corn rise on new seeds http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/18/monsanto-eyes-ri-s-corn-rise-new-seeds.html
Jakarta Postの記事(2013/05/18)。遺伝子組み換え種子をフィリピンに、と。 - 2013/09/27 Cultivation of GM crops, plants urgent: Farmers http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/27/cultivation-gm-crops-plants-urgent-farmers.html
Jakarta Postの記事(2013/09/27)2014年に遺伝子組み換えサトウキビ、遺伝子組み換えトウモロコシの栽培が始まる可能性を伝える。
フィリピン:遺伝子組み換えと闘う農民たち
昨年10月に発表されたフィリピンのMASIPAG(Farmer-Scientist Partnership for Development、農民と科学者の発展のためのパートナーシップ)による『10年の失敗—GMコーンに騙された農民たち』のビデオドキュメンタリー、MASIPAGの協力やAPLAのボランティアの協力で日本語字幕版を作成した。
遺伝子組み換え問題に関するビデオは数多くあるが、ここまで農民の口から遺伝子組み換えがもたらす問題がなまなましく語られたドキュメンタリーは類を見ない。
25分弱にわたるものだが、ぜひご覧いただきたい。
このドキュメンタリーではモンサントが遺伝子組み換えが何であるか、まったく農民には情報をもたらさないまま、高収穫、高利益を与えるという偽りの宣伝で農民を騙す形で導入されていくことが語られる。
安かった種子は高くなり、肥料や農薬は年々必要量が増えた上、値段も上がり、農民は債務で土地を失い始める。そして、それまで主食の一部にもなっていたトウモロコシの種子を失った時、彼らは自分たちの食べるトウモロコシを買わなければならなくなってしまったことに気がついた。
自分が作ったGMコーンを食べれば下痢になり病気になる。カラバオ(水牛)に食べさせたら死んでしまう、という証言は衝撃的だ。米国の農民にとってGMコーンは自分たちが食べるものではないし、家畜も工場のようなところで数ヶ月餌付けするだけなので、どんな健康被害があるのか、知ることは難しい。しかし、主食に近いものとしてトウモロコシを食べ、さらに家畜が家族のように長く付き合う存在であるフィリピンの農民にとってはそのGMコーンが健康に与える影響はずっとはっきりと見えるのだろう。それだけにこれは欧米で作られたドキュメンタリーよりもはるかに生々しいものになっているのだ。
さらにGMコーンの導入後、土壌流出が続き、農地が石ころだらけになってしまったという。さらにGMコーンにかける有毒な除草剤が周辺のバナナやマンゴーも病気にしてしまう。
トウモロコシは自家受粉で実を付ける大豆と異なり、花粉が遠くまで運ばれてしまうので、GMコーンを始めるとその周辺のトウモロコシも汚染されてしまう。GMコーンをやめたくても、自分だけやめても汚染されてしまうし、さらに強力な農薬が流れてきてGMコーン以外は育たない環境になってしまう。
遺伝子組み換えにより、農民は種子を失い、食料を失い、土地を失う結果となった。その一方で、モンサントやデュポン(パイオニア)などの遺伝子組み換え企業は大きな利益を上げている。
こうした動きに対して、遺伝子組み換えをやめ、有機農業によって村を変えていこうとする動きが出ている。個々の農家だけで変えようとしてもGMコーンによる汚染や農薬流出もあって、変えることは困難だが地域がいっせいに変わることで、この悪循環を止めることは不可能ではない。
その困難な闘いがフィリピンで進められていることをまずこのビデオから知ることができる。
なお、このMASIPAGの調査は80ページの詳細なレポートにまとめられており、全文をダウンロードすることができる。
ダウンロードはMASIPAGのサイト: Socio-economic Impacts of Genetically Modified Corn In the Philippines (2013年9月 PDF 2.1MB)
2014年2月20日追記
25年目のオルタナティブをめざして
上田誠(オルター・トレード・ジャパン代表取締役)
今年2014年は国連食糧農業機関(FAO)が定める国際家族農業年です。なぜ、今年が国際家族農業年となったか、そこには大きな危機意識があります。このまま企業的大規模経営農業が進んでいくと、世界の飢餓や貧困が増加し、気候変動がさらに激化し、地球規模で破局的問題に陥るという認識が広がりつつあるのです。
グローバリゼーションの拡大に伴い、多国籍企業の影響力はより強大になり、日本を含めた世界規模の問題となってきました。実際、フィリピンではミンダナオ島など遺伝子組み換えトウモロコシ畑が広がり、その影響で自立した生産者の営みはより困難な状況に陥っている地方があります。フィリピンはもちろん、日本を含むアジアでも、EUや米国、アフリカ、ラテンアメリカでも食の安全よりも、多国籍企業の利益を追求する大規模農業が力を拡大してきました。
私たち日本人の食生活にも遺伝子組み換え食品はすでに深く浸透しています。日本に輸入される大豆の75%以上、トウモロコシの80%以上、ナタネの77%以上が遺伝子組み換えになっていると言われ、日本の食料依存、特に遺伝子組み換え依存はますます高まりつつあります。
安心できる食を確保していくことは、それを生産する国内外の小規模生産者を守る活動と切り離すことはできないとATJは考えます。近年、アグリビジネスによる大規模農業に支配されない小規模生産者主体の農業を作り出す運動が世界各地に現れています。日本ではまだ聞き慣れぬ言葉ですが、アグロエコロジーという生態系を守り、食の安全と職の確保を求める農業運動がラテンアメリカでもアフリカでも大きく成長しつつあります。
この動きは、南の国だけでなく、フランスや米国、英国などの国々で現在の農業に対するオルタナティブであり、気候変動を抑え、飢餓問題を解決できる農業であるとして注目され始めています。すでに、フランス政府の政策にも反映され始め、FAOはこのアグロエコロジーを世界的に推進するために国際的な小農民運動団体であるVia Campesina(ビア・カンペシーナ)と連携することを発表しています。
こうした流れの中に今年の国際家族農業年があります。国連貿易開発会議は「手遅れになる前に目覚めよ」という激烈なタイトルを持つ報告書で企業的大規模経営モノカルチャー農業を小規模家族農業、アグロエコロジーへの転換を一刻も早く進めることを求めています。
国際家族農業年は、家族農業が持つ社会的、文化的、自然的な役割と価値が、小規模生産者のくらしを改善し、持続的な生産を実現し、現在私たちが直面している飢餓人口の削減や貧困の削減といった様々な問題に対抗しうる力となりうることも、提示しています。
世界で生まれているこうした流れはオルター・トレード・ジャパン(ATJ)にとっても重要な動きです。 私たちATJは民衆交易という生産と消費の場をつなぐ交易を通じて、「オルタナティブ」な社会のしくみ・関係を作りだすことを目的として、フィリピンを始めとする各国の生産者・パートナーとつながりを深めてきました。
フィリピンでは多国籍企業が生産するプランテーションバナナではなく、裏庭にあるバランゴンバナナの交易を通じて、小規模生産者の自立を求めて取り組みを進めてきています。同様の地域に根差した取り組みは、インドネシア、東ティモール、パレスチナ、ラオス、そしてパプアに現在広がっています。
2014年、ATJが民衆交易を開始してちょうど25周年を迎えます。同年に国際家族農業年が決定されたことに深い意味を感じます。なぜならば、ATJが25年間のアジアの小規模生産者との取り組みを通じて感じている私たちの危機感と、国際家族農業年にはっきりと現れた世界農業の危機認識が重なったからです。
残念ながらこうしたオルタナティブを求める世界の動きは日本ではほとんど報道されません。企業的大規模経営農業、「競争できる農業」ばかりが推奨され、TPP交渉や国家戦略特区などを通じてそうした農業が政府の支援を受け、強化されようとしています。しかし、残念ながらそこに日本と世界の安心できる食の未来は見いだせません。
ATJはこうした世界のオルタナティブな試みに光をあてるため、「世界のオルタナティブ」というWebサイトを開設しました。世界で躍進するアグロエコロジーのさまざまな試み、遺伝子組み換えやアグリビジネスと対決する小規模生産者の動き、消費者・市民の取り組みなどをお知らせしていきます。
そして、その第一歩として、フィリピンのパートナーとともに、バランゴンバナナを通じた民衆交易が切り開く可能性を共同で調べる調査プロジェクトを開始いたします。そのプロジェクトをみなさまと共に進めていくために2014年3月16日に『バナナと日本人』その後 -私たちはいかにバナナと向き合うのか?と題したセミナーを開催いたします。
今後も世界のネットワークを活かして、「ひとからひとへ、手から手へ」わたされる民衆交易によって共同体・地域づくりを進めながら、オルタナティブを求める世界の小規模生産者の営みを伝え、今後も食と職、農と地域のあり方を豊かにしていくための提言と取り組みを進めて行きます。
ぜひ、みなさまもご参加いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 セミナー詳細: 『バナナと日本人』その後 -私たちはいかにバナナと向き合うのか? 2014年3月16日14:00~17:00 東京・池袋立教大学にて
セミナー詳細: 『バナナと日本人』その後 -私たちはいかにバナナと向き合うのか? 2014年3月16日14:00~17:00 東京・池袋立教大学にて