カテゴリー: レポート(エコシュリンプ)
エコシュリンプ
エコシュリンプとブロッコリーのオリーブオイル炒め
<材料2人分>
●エコシュンプ下処理済(Lサイズ、殻つきでもOK)・・・7-9尾
●ブロッコリー・・・お好みの分量
●パレスチナのオリーブオイル・・・大さじ2
●にんにく・・・1かけ
●ゲランドの塩・・・適量
<作り方>
1. エコシュリンプは解凍し水気をきっておく。(殻つきの場合、尾だけ残して殻を剥き、背ワタもとる。)
2. ブロッコリーは一口サイズに切り、さっとゆでておく。(ゆで過ぎに注意!)
3. にんにくはスライス。
4. 軽く熱したフライパンにオリーブオイルをまわしいれ、にんにくをいれ、香りがたったらエビを投入。エビの色が少し変わってきたら、ブロッコリーも入れて炒める。
5. エビに火が通ったら(きれいに赤くなります)、塩で味をととのえて出来上がり。
ポイント① 背に切り込みをいれると、味がしみこみやすくなります。
ポイント② エコシュリンプとパレスチナのオリーブオイルとの相性は抜群!エビの香りが移ったオリーブオイルは、パンにつけたり、他のお料理にも使えます。
ポイント③ 殻まで美味しいエコシュリンプ。たっぷりの油で炒めるとパリパリとした食感と旨みが楽しめます。
エコシュリンプ~スラウェシ島での新たなチャレンジ~ from インドネシア
遡ること27年前、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)は、インドネシアから粗放養殖のブラックタイガー、「エコシュリンプ」の輸入・販売の事業を開始しました。
日本のエビ消費の裏側で
日本でエビの輸入が自由化されて以降、エビ好きな日本人の胃袋を満たすべく、天然エビが乱獲され、水産資源の枯渇が問題化した1960~1970年代。
それに代わるものとして、台湾で生まれた「親エビ革命(※)」というエビの養殖技術が、80年代にアジア各地に広がりました。
しかし、大量生産が可能な集約型養殖池の開拓により地域の自然が破壊され、養殖池では人工飼料や抗生物質が、収獲後にも薬が多用され、食品としての安全性が問題となりました。
「子どもたちも安心して食べさせられて、産地の環境にも負荷をかけないエビを買いたい」という消費者の願いと、集約型養殖池による環境破壊と汚染を非難し、「土地は子孫からの預りもの。次の世代へ引き継いでいかなくてはならないもの」という思いで粗放養殖を営む生産者との出会いから始まったエコシュリンプ事業は、ジャワ島東部から、スラウェシ島南部の生産者にも広がり、今に至ります。
※大量養殖のために、エビの眼を人為的に切断する技術。両眼を順番に切り落とす事で、エビは抱卵しやすくなり、稚エビの大量供給が可能となった。
後発産地スラウェシのジレンマ
ジャワ島東部では有機認定システムの導入や現地法人オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)の立ちあげ、自社工場の設立と、エコシュリンプ事業を展開。
池への放流後に無給餌、無投薬の条件を満たす粗放養殖エビであることが、買入れ前に確認されている」というエコシュリンプの定義に適ったエビを日本の消費者に届けるために、生産者との関係強化・深化に取り組んできました。
一方で、後発産地であるスラウェシ島では、基準を満たすエビの買い付けを続けながらも、生産者との関係を深められないまま10年以上の月日が流れてしまいました。
とはいえ、ATINAはスラウェシの生産者との対話を通じ、また、刻々と変わる養殖環境の中で創意工夫しながら鋭意エビを育てている生産者の姿を目の当たりにし、いつかこのスラウェシ島でもジャワ島で取り組んできたような、エビの買い付けに留まらない活動を生産者と共に始めたいという思いを強くしていきました。
生産者のストーリーを伝える
2018年夏、ATINAは「アジアの水産物の向上のための協働体(ASIC)」と共に念願だったスラウェシ生産者との活動を開始しました。
ASICは、アジアに拡がる水産品の生産者組織、加工工場、環境NGOや認証団体などで構成された協働体で、バイヤーや輸出業者と共に地域の水産業の持続性や労働環境の改善などなど)などに取り組むことを目的に活動している組織です。
近年、持続可能な水産物に関する消費側の関心は高まり、そうした水産品の認証制度も徐々に認知されてきています。
一方で、認証制度を導入できるのは、費用負担が可能で複雑な記録作業やマネージメントの能力を備えた中規模、大規模の生産者団体や企業に限られており、市場に出回る水産品の供給を下支えする小規模な生産者にとっては高いハードルがあるのが現状です。
ATINAとASICは、認証制度に頼るのではなく、エコシュリンプの生産者のような小規模な生産者たちの生の声を拾い、生産者が持続的に粗放養殖を続けてゆくために必要な取り組みを行い、それを「ストーリー」として消費者に伝えることで、そのような水産物が消費者の選択肢の一つとなることを目指しています。
現時点では、今後の具体的な活動につなげてゆくためのワークショップを開催しています。テーマは、エビ産業における女性の活躍、生産者の組織化、環境変化によって影響を受けやすい粗放養殖を続けていくためのリスクヘッジなど、多岐にわたりますが、生産者の置かれている状況をより理解してゆくための大事なプロセスと考えています。
地道な活動ではありますが、これからもエコシュリンプ届けながら、スラウェシの生産者との取組みについても、お伝えしていきたいと思います。
山下万里子(やました・まりこ/ATJ)
【PtoP NEWS vol.30 ここが知りたい!】エビの「プリプリ」の秘密(ひみつ)
エビを普段は余り買わないけれど、お祝いごとの時ばかりは買う、という方も多いかと思います。
エビの赤い色彩はお料理に華やかさを添えますが、その魅力はなんといっても、あのプリプリとした食感と口の中にひろがる風味でしょう。
エビを口にした時の、はじけるような噛みごたえとプリプリとした食感、実は人工的につくられていることがあるのをご存知ですか?市販のエビは、食感を良くするために「保水剤」という薬剤を使用していることがあります。
たんぱく質が豊富なエビの身は、生だと半透明ですが、身も加熱すると本来は白く変色します。一方で人工的に保水されているエビは、加熱してもエビの身が半透明のまま。そして味はというと、保水されていないエビと比較するとその差は歴然です。保水によって味が薄まってしまい、ほとんど味がありません。
インドネシア産の粗放養殖のブラックタイガー「エコシュリンプ」は池の中でのびのびと泳ぎ回っていて筋肉質なうえに、「保水剤」は使っていないので、口に入れると「プリプリ」の食感と、ブラックタイガーならではの濃厚な味わいが楽しめます。
山下万里子(やました・まりこ/ATJ)
【PtoP NEWS vol.21 ここが知りたい!】日本の市販エビ
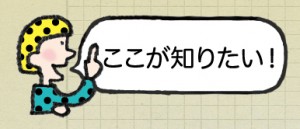 スーパーでエビをジッと眺めると、大体がバナメイだと思います。iPhoneが登場した10年前には、まだブラックタイガーが主流でした。
スーパーでエビをジッと眺めると、大体がバナメイだと思います。iPhoneが登場した10年前には、まだブラックタイガーが主流でした。
両者の共通点は、「養殖しやすい」こと。ですがここ10年強でバナメイの生産量は一気に拡大し、1999年にはゼロだった東南アジア産バナメイは、今や世界の80%を占めているという事態です。
 病気に強く、また泳ぎ回るために養殖池の深さを活用できるバナメイは、瞬く間に養殖エビ業界のスターにのし上がりました(一方のブラックタイガーは池底を歩き回るだけなので、池底の面積分しか活用できない)。
病気に強く、また泳ぎ回るために養殖池の深さを活用できるバナメイは、瞬く間に養殖エビ業界のスターにのし上がりました(一方のブラックタイガーは池底を歩き回るだけなので、池底の面積分しか活用できない)。
小さいので安価なところもウケたようです。
 しかし2013年、最大の輸出国であるタイで病気が発生し、世界のエビ供給は激減。価格が暴騰し、「てん屋」からエビ天が消える事態にまで発展しました。
しかし2013年、最大の輸出国であるタイで病気が発生し、世界のエビ供給は激減。価格が暴騰し、「てん屋」からエビ天が消える事態にまで発展しました。
やはり、集約的に給餌する養殖方法にはどこか無理があるようですが、そんなことは表示を見てもわかりません。
表示と言えばもう一つ。「製造者(もしくは加工者)」とか「販売者」とか書いてあれば、それは国内で何らかの手が加えられた証拠。エビの場合、大抵は一度解凍されて再凍結されたり保水処理*をされたり、ということです。pH調整剤と書いてあっても、その目的は保水かもしれません。エビ一つをとっても、結構色々なことが見えてきます。
*解凍したときなどにエビから水分が出ないよう保水剤が用いられる処理。
若井俊宏(わかい・としひろ/ATJ)
スラウェシ島地震・津波被災者に、ATINAスタッフが支援物資を送りました。
インドネシア・スラウェシ島中央スラウェシ州で、9月28日に発生したマグニチュード7.5の地震とそれに伴う津波の影響で、多くの犠牲者が出ました。
同島南スラウェシ州ビンラン県周辺には、エコシュリンプの養殖池がありますが、オルタートレード・インドネシア社(以下ATINA)スタッフ、並びにエビ生産者の人的な被害はありませんでした。
その後、甚大な被害状況が明らかになったことを受けて、ATINAの職員及び工員は、10月3日より、義援金、インスタント食品、医薬品、毛布、テント、衣料品などを集め、スラバヤ市を通じて、被災地に届けることにしました。
被災地の一日も早い復興と現地の皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
【PtoP NEWS vol.19/2017.10】池の丸干し from インドネシア (エコシュリンプ)
井の頭池の「かいぼり」にインドネシアへの思いを馳せる
ナウなヤングのデートのメッカ、東京は吉祥寺にある井の頭公園は、今年めでたく開園100周年を迎えました。井の頭公園の見どころと言えば、神田川の出発点でもある井の頭池。カップルでボートに乗ると必ず別れると噂されるこの池は、それでも休日には所狭しと人工スワンが行き交い、天然カモはのびやかに泳ぎ回り、春には桜の花びらが色を添えます。
そんな井の頭池、かつては水が透き通っており、池底まで見えるほどだったそうです。しかし高度経済成長のあおりを受けて湧水量が減少。
その結果、池水の滞留時間が長くなったことで植物プランクトンが増加し、池の水は濁り、在来生物は減少し、外来生物が幅を利かせるようになってしまいました。そこで、100周年を迎えるにあたり、地元の人びとが「井の頭池をよみがえらせよう!」と立ち上がり、始まったのが「かいぼり」でした。
2014年から、数回に分けて行われたこの「かいぼり」。簡単に言えば、池の水を抜いて池底の土を天日干しすることと、そこにいる生き物を捕まえて仕分けし在来種だけを池に戻す、という取り組みです。それにより、土の地力が回復して水草が育ち、そこに在来種を戻すことで、本来の生態系に近づけていくことができるのです。もう誰も自転車を捨てたりしなくなるのです。
しかし、エコシュリンプを知る人にとっては、井の頭池は、エビの養殖池にしか見えません。目を閉じると、そこには平米当たり3尾の割合で放流された稚エビとバンデンが、仲良く泳ぎ回っています。
薄目を開けると、井の頭弁財天は養殖池にある管理人の小屋に見えてきます。思わずパンツ一丁でエビを獲りに入水したくなりますが、実際に入ってみると、池底はそれほど柔らかくはなく、エビもいませんでした。水も、インドネシアよりは冷たいです。その後は厳しい現実が待っています。
エコシュリンプの養殖池でも「かいぼり」
さて、インドネシアに広がる粗放養殖池には、ナウなヤングも人工スワンもいませんが、大人の階段を上るエビと魚はたくさんいます。
そして、古いところでは、めでたく300周年あたりを迎えているはずです。
乾季になると、「かいぼり」と同じように水を抜き、残ったエビや魚を獲り、池の底を天日にさらします。ヒトは吉祥寺でもジャワ島でも、同じようなことをして生きています。
水を抜いた養殖池は、赤道直下のガンガンの日照りにさらされ、池底の粘土質土壌は煉瓦のようにカチカチになります。
布団干しと同じで、これにより土が紫外線殺菌されるそうです。このカチカチ状態で1ヶ月くらい放置し、完膚なきまでに乾燥させるのが、本当の池干しのようです。その間に、池の土をひっくり返すこともあります。炎天下、数ヘクタールの池でこの作業をするのは、非常な重労働です。
地球の変化は養殖池にも
なぜエビ養殖のために土を大切にするのか?もちろん環境を整えるためなのですが、特に重要なのは、水草の生育です。
土づくりがうまくいかないと、いざ養殖を始めた時に水草が良く育ちません。すると、植物プランクトンの発生が少なくなり、稚エビが食べるエサが少ないことになり、結果的にエビの生育が悪くなります。
さらに、日中の光合成が減るために水中の酸素が不十分になったり、水面を覆う部分が少なくなることで昼夜の水温変化が激しくなったりと、見えないところでもエビの生育に影響を与えるそうです。もちろん、水草が多ければいいというものでもなく、適切な割合が望ましいです。
生産者に聞くと、「水面の40%を覆うくらいがいい」など、色々な意見を聞きますが、あまり共通見解はありません。各々の信念に基づいている部分もあるようです。
このようにエビの粗放養殖にとって重要な池干しですが、自然に依拠した養殖方法ゆえに、お天道様には逆らえません。
最近は地球温暖化の影響か、乾季と雨季の境目がはっきりせず、本来の乾季にも雨が降り続き、満足な「干し」ができないのです。
これがエビの生存率を悪化させている、と言う生産者もいます。昔から続く養殖方法に影響を与えるほどの環境変化は、決して小さくはなく、養殖池の池干し一つとってみても、実は地球はつながっているということを感じないわけにはいきません。日々の生活をちょっとでも見直すきっかけになれば、と思います。
若井俊宏(わかい・としひろ/ATJ)
オルター・トレード・インドネシア(ATINA)社が、インドネシア海洋水産省から「全国最優良エビ加工工場賞」を受賞しました。
エコシュリンプを製造するATINA社は、インドネシアの海洋水産庁から「全国最優良エビ加工工場賞(The best winner with category “Shrimps Processing Factory)を受賞しました。なかでもHACCPとトレーサビリティのシステムにおいて、全国最優良と評価されました。
2014年12月4日、ATINA社ゼネラルマネージャーのハリー・ユリが、ジャカルタの大統領宮殿で表彰状とトロフィーを授与される儀式があり、その後に海洋水産省主催のパーティーに参加しました。
ATINA社では、これまでの品質管理・トレーサビリティーに対する、関係者全員の取り組みが評価されたことを、皆で喜んでいます。
村井吉敬さんがご逝去されました
村井吉敬氏(早稲田大アジア研究機構教授)が23日、すい臓がんのためご逝去されました。
『エビと日本人』(岩波新書)の著者としても知られる村井先生。1991年2月、
生協関係者や堀田ATJ前社長とともに、環境に優しい養殖エビを探しにインドネ
シアを訪れました。東ジャワで池を耕し、堆肥を施してエビを育てるハジ・アム
ナン氏との出会いがエコシュリンプ事業につながりました。エコシュリンプの生
みの親と言っても過言ではありません。
24日に執り行われたATINA新工場開所式では、冒頭に全社員が黙祷をささげ、村
井先生の思いを胸に決意を新たにしました。
今年度より開始されたATJカカオ事業では、カカオの産地、インドネシア、パプ
ア州に足繁く通った村井先生から事業化にあたっていろいろと提言を頂きました。
村井先生のご冥福を心からお祈りいたします。
ATINA新工場完成間近です!
2009年から構想し、2012年8月より建設工事に着工したATINA新工場も、いよいよ完成が目前に迫ってきました。ATINAでは2月半ば現レンタル工場での最後のエコシュリンプ製造を終え、工員さんの中には「(この工場で働いた)8年間で、オートバイ買って、結婚して、子ども生んで、家を建てたのよねー」と感慨深く振り返る人もいました。今度の新しい工場では、どんな夢を実現していくのでしょうか。
さて追い上げの建設作業の方ですが、監査員たちは自分たちの事務所建設の最後の仕上げに取り組むなど、建設業者が雇っている日雇い労働者に混じって、ATINA従業員も一緒に汗水流しています。廃水処理施設の建設には日本の専門家から指示を仰ぎながら、ATINA技術者や品管担当者が溶接や配管などを器用にこなしています。そして3月5日より、工員さんたちも初めて新しい加工場に入り、新品の機械や加工ラインの掃除を開始。3月24日の新工場落成式に向けて、ATINA従業員総出の作業はますます拍車がかかってくることでしょう!
津留歴子
エコシュリンプでオルタナティブな食を|クッキングスタジオBELLE料理教室
11月13日、生活クラブ・クッキングスタジオBELLEで、エコシュリンプ20周年記念クラス料理教室「エビをおいしく~えびたっぷり和のメニュー~」が開催されました。
 メニューは、お正月の装いをしたエコシュリンプでした。エコシュリンプのむきみを使った“えびしんじょうのお椀”、棒書紙を巻いたように見せる“棒書揚げ”は、まるで内掛をまとったかと思えるエコシュリンプでした。そして季節の野菜たちとお皿を華やかに彩る“えびの黄金焼き”。どれもエコシュリンプの旨みや食感を大切に引き出すレシピです。エコシュリンプの旨みは、ボイルかオリーブオイル炒めと決めつけていましたが、季節の装いやさまざまな食文化の装いでたくさん楽しめる素材だと実感しました。
メニューは、お正月の装いをしたエコシュリンプでした。エコシュリンプのむきみを使った“えびしんじょうのお椀”、棒書紙を巻いたように見せる“棒書揚げ”は、まるで内掛をまとったかと思えるエコシュリンプでした。そして季節の野菜たちとお皿を華やかに彩る“えびの黄金焼き”。どれもエコシュリンプの旨みや食感を大切に引き出すレシピです。エコシュリンプの旨みは、ボイルかオリーブオイル炒めと決めつけていましたが、季節の装いやさまざまな食文化の装いでたくさん楽しめる素材だと実感しました。
受講者の方たちが試食される間に、BELLEマネージャーの近藤惠津子さんに代わって、ATJから環境に配慮したエコシュリンプの養殖方法についてお話しさせていただきました。
 クッキングスタジオBELLEとは、「安心・安全な食生活を送り、食べ物を生産し続けられる地球を維持するために、食を追求する場」と謡われています。そして「食を楽しむ」場でもあると近藤さんは言います。使う食材や料理方法はサステイナブル(持続)に繋がり、そして受講生の皆さんもグループでお料理を仕上げることからチーム力のある人間関係ができるそうです。
クッキングスタジオBELLEとは、「安心・安全な食生活を送り、食べ物を生産し続けられる地球を維持するために、食を追求する場」と謡われています。そして「食を楽しむ」場でもあると近藤さんは言います。使う食材や料理方法はサステイナブル(持続)に繋がり、そして受講生の皆さんもグループでお料理を仕上げることからチーム力のある人間関係ができるそうです。
生産する人、流通する人、料理する人、そして食べる人、皆の想いがつながって持続的な社会ができるのだと近藤さんは語ります。また、「セミナー&クッキング 食の安全」クラスでは、11月のセミナーでは「世界の養殖~エビ~」と題して水産物の消費の現状、そしてエコシュリンプのお話しでした。
クッキングスタジオBELLEのプログラムは近藤さんが理事長を務めるNPO・CSまちデザインによって運営されています。
近藤さんは生協に入ることをきっかけに食の安全、食(生産)の持続、暮らしのあり方に関心を持ち、生協活動のリーダーとして活躍する中で、直接運動には参加しなくても、サステイナブルな社会の必要に気付く人々を増やしていきたいと考え始めました。生協で学び培ってきたことをさまざまな形で発信することで、サステイナブルな社会づくりをめざすゆるやかなうねりをつくるために、CSまちデザインを設立しました。
CSまちデザインは、生活クラブの人材育成プログラムである「食のコンシェルジュ養成講座」、その活動の一環として「クッキングスタジオBELLE」の企画・運営を担う一方、独自の講座や講師派遣なども行なっています。
そして、CSまちデザインのもうひとつの活動が、学校教育の場での“食農共育”です。子どもたちにも食を通して豊かな暮らしや人間関係を伝え体感して欲しいと奔走しています。講座や授業を通じて「世界一エビを食べるといわれている日本人、子どもたちが大好きなエビ、そうしたエビを日本人が食べることで地球環境が破壊されている実態があるなかで、エコシュリンプは、そうではないオルタナティブな食のあり方を具体的に提案してくれる重要な素材です」と語ってくれました。
(ATJ交流企画事業推進室・幕田恵美子)
【エコシュリンプ生産者来日】|国を越えた交流へ(野付訪問その2)
 国際協同組合年である今年の「協同組合地域貢献コンテスト」で、215件の中から4件の最優秀賞に輝いた野付漁協。その取り組みは「植樹を通じた環境保全活動と生協との産直交流」です。そして今回、彼らが野付にお邪魔した最大の目的は、前日の資源管理型漁業について学ぶことに加え、植樹を通じた交流活動に他ならないのでした。
国際協同組合年である今年の「協同組合地域貢献コンテスト」で、215件の中から4件の最優秀賞に輝いた野付漁協。その取り組みは「植樹を通じた環境保全活動と生協との産直交流」です。そして今回、彼らが野付にお邪魔した最大の目的は、前日の資源管理型漁業について学ぶことに加え、植樹を通じた交流活動に他ならないのでした。
その日の早朝。まだまだ10月はそれほど寒くないとは言え、「初めて体験した」と言わしめる気温の中、漁港に彼らの姿がありました。深夜に定置網漁に出た漁船が帰港し、秋サケをはじめ、水揚げされた水産物の数々。中には見知った魚もあるとのこと。それらがどのように選別され、管理されているのか・・・きりっと冷えた頭で視察しました。
 朝食では特別な計らいで、揚がったばかりのカレイを煮付けて頂くという贅沢。定番の秋サケの塩焼きも含め、一週間かけてじっくり楽しみたいくらいの大量の魚をきれいに平らげ、メインイベントの植樹へ。自分達の名前が書かれたプレートが準備され、参加者全員がめいめいに土を掘り、汗を流して木を植える営みは、それだけで十分心に残るものとなりました。そして、恐らく初めてではないかと思われる外国人である彼らの名前は、未来永劫この野付の地に刻まれることとなったのでした。
朝食では特別な計らいで、揚がったばかりのカレイを煮付けて頂くという贅沢。定番の秋サケの塩焼きも含め、一週間かけてじっくり楽しみたいくらいの大量の魚をきれいに平らげ、メインイベントの植樹へ。自分達の名前が書かれたプレートが準備され、参加者全員がめいめいに土を掘り、汗を流して木を植える営みは、それだけで十分心に残るものとなりました。そして、恐らく初めてではないかと思われる外国人である彼らの名前は、未来永劫この野付の地に刻まれることとなったのでした。
周りを見渡してみると、かなりの数のネームプレート。この場所も、数十年後には森になるはずです。「100年かけて、100年前の自然の浜を取り戻そう」というこの運動には、とても多くの人が関わっていることが実感できました。今回は「クマが出る」ために残念ながら車からの見学となりましたが、実際にほぼ森状態になった場所では、新しく湧き水が湧き始めたとのこと。まさに「継続は力」であることがわかります。
 さて、このように人々の力と継続的な運動が実を結んだ様を目の当たりにして、彼らは何を考えたのか? インドネシアに帰った彼らは、今回の体験をどのように仲間へ伝え、今後どのような活動につなげていくことができるのか?今までにない、海を越えた交流活動は、まだまだ始まったばかり。この関係をこれからも継続し、具体的な次へのアクションにつなげていくことを心に誓い、中標津空港を後にしたのでした。
さて、このように人々の力と継続的な運動が実を結んだ様を目の当たりにして、彼らは何を考えたのか? インドネシアに帰った彼らは、今回の体験をどのように仲間へ伝え、今後どのような活動につなげていくことができるのか?今までにない、海を越えた交流活動は、まだまだ始まったばかり。この関係をこれからも継続し、具体的な次へのアクションにつなげていくことを心に誓い、中標津空港を後にしたのでした。
末筆となりますが、このような貴重な機会を与えてくださった野付植樹協議会の皆様に、心より御礼申し上げます。
【エコシュリンプ生産者来日】|資源管理型漁業について学び、海の幸を堪能する(野付訪問その1)

今回のエコシュリンプ生産者来日の背景の一つは、野付植樹協議会の設立10周年を記念して2012年3月にインドネシアで行われた交流がきっかけでした(当時の報告はこちら。インドネシアで持続的なエビ養殖を営んでいるエコシュリンプ生産者に、今度は野付の資源管理型漁業を見せたい!という有難いお招きに預かり、この度の訪問が叶ったわけです。
さて、乾季で暑いインドネシアから初来日の翌日、羽田空港に集合してさっそく中標津空港まで飛んだレギミンとアサッド。空から見える広大な牧草地を珍しそうにしげしげ眺めるアサッドと、その横で揺れに怯えて縮こまるレギミンが、対照的でした。
 牧草とウシの香る中標津空港から、一路野付漁協へ。ヒトよりウシが多く、あまりに通行人が少ない様子に驚きながらも、広大な土地の真ん中での快適なドライブでした。野付漁協では、3月にインドネシアでお会いした懐かしい皆様がお出迎え下さり、早速、北海道の漁業の概要から、野付漁協の資源管理型漁業への取り組みレクチャーを頂きました。
牧草とウシの香る中標津空港から、一路野付漁協へ。ヒトよりウシが多く、あまりに通行人が少ない様子に驚きながらも、広大な土地の真ん中での快適なドライブでした。野付漁協では、3月にインドネシアでお会いした懐かしい皆様がお出迎え下さり、早速、北海道の漁業の概要から、野付漁協の資源管理型漁業への取り組みレクチャーを頂きました。
北海道の年代別漁業就業者は、やはり50代以上が中心。そして全体的には減少傾向にあります。それを見たアサッド(=50歳、孫あり)は、しみじみと一言。「高齢者ががんばって支えているのか・・・」。シドアルジョのエビ生産者でも同じような傾向はあるようで、人事ではないと感じた模様。アサッドにはまだまだ現役で頑張ってもらうとしても、今回残念ながら来られなかったイルルのような若手生産者も一緒に支え合って行ける関係が、これからのエコシュリンプには求められているのです。
 一方、資源が豊富な野付地区の漁場で資源管理型漁業が始まった背景は、乱獲や環境変化による水産資源の枯渇でした。現在は、稚貝の放流や親魚の捕獲を計画的に実施すると共に、漁獲の前には資源量調査を行い、獲り過ぎにならないように漁業制限を設けながら、水揚げを行っています。漁協の組合員もそのことを理解し、「譲りと協同」の思想の下、個々人の漁獲高に固執しない漁業が営まれているのです。
一方、資源が豊富な野付地区の漁場で資源管理型漁業が始まった背景は、乱獲や環境変化による水産資源の枯渇でした。現在は、稚貝の放流や親魚の捕獲を計画的に実施すると共に、漁獲の前には資源量調査を行い、獲り過ぎにならないように漁業制限を設けながら、水揚げを行っています。漁協の組合員もそのことを理解し、「譲りと協同」の思想の下、個々人の漁獲高に固執しない漁業が営まれているのです。
インドネシアではまずお目に掛かることの無いこの取り組み。まずアサッドからは「どういう意識があると、そういうことができるのか!?」と驚き混じりの質問があり、続いてレギミンからは「漁獲制限は政府から割り当てられるものなのか?」と、これも不思議な表情。「自分達で決めて進めていく」という野付漁協のあり方が、まずは彼らにとって斬新だったと言えます。それでも、「守らない人にはペナルティーも辞さない」という徹底振りに、「将来を考えた取り組みを、協同で自発的に進めている点」が少なからず腑に落ちたようです。
夜は、そんな野付半島で獲れた海の幸を堪能。さすがに生のホタテやイクラには抵抗があったものの、野付漁協のご好意によって「ホタテ揚げ」に変身した途端、旺盛な食欲で頂きました。なお、かの有名な「北海しまえび」を山ほど食べたことは、言うまでもありません。
(報告:商品課 若井俊宏)
エコシュリンプ: 壁の内側では何かが起こりつつあるようだ-ATINA自社工場建設(2)

とりあえずサトウキビの侵入を食い止めたい壁の基礎(2012.2月)
「うなぎの寝床」整地完了から、早半年・・・。その間、本物のうなぎは高騰の一途を辿り、土用丑の日に精力を付けられなくなった多くの日本国民に熱中症をもたらすこととなりました。
一方、インドネシアのシドアルジョにおいては、暑さ慣れしているインドネシアの人々により、着々と新工場の建設準備が進められています。隣に残るサトウキビ畑との境界には、長さ500メートルのコンクリート壁が毅然と張り巡らされ、ようやく何か建物ができることを予期させる風景へと変貌を遂げました。
 |
|
| 急ピッチで壁建設(2012.2月) |
ネズミ一匹入らせまいという断固たる決意が感じられる500mの壁とこれから何かすごいものができそうな予感のする細長い土地(2012.3月)
|
敷地内では下から順に工事が進み、まずは製造中に使う水を貯めておくためのスペースが掘られています。
 |
 |
|
泳いだら気持ち良さそうなプールに見えるタンク予定地(2012.7月)
|
タンク予定地2(2012.7月) |
工場の背面になる敷地の奥では排水用のタンクも掘られ始め、そこには、かの有名なBMW技術が導入される予定です。これで排水も今まで以上にキレイになり、より環境負荷の小さい低い次世代工場へと進化することができます。

さっそく水が溜まって準備万端な排水タンク予定地(2012.7月)
新工場では、従来の冷凍エビとしての「エコシュリンプ」に加え、エコシュリンプを使った加工品の製造や、エビ以外の製品も視野に入れた稼動を目指しています。また、冷凍倉庫、石けん工房、分析室などが一箇所に集約され、より無駄の少ない効率的な稼動ができるようになります。
明るく元気で丈夫な工場が生まれますよう、これからも応援の程、宜しくお願い致します!
商品課 若井俊宏
資源管理型漁業をテーマに交流-|日本の漁協がエコシュリンプ産地を訪問
北海道でホタテの養殖や、エビやサケなどの出荷や加工などを行っている野付漁業協同組合と、北海道漁業協同組合連合会、パルシステム連合会が組織する「海を守るふーどの森づくり野付植樹協議会」が、2012年3月20日~26日までインドネシアのエコシュリンプ産地を訪れ、資源管理型漁業をテーマに視察・交流会が行われました。
【3月21日】スラバヤから近いパスルアン県の沿岸住民であったムカリムさんは、家を侵食から守るために1986年から15年間ひとりでマングローブを植え続けました。やがてカニや魚が戻ってくるとコミュニティの人々も植林活動に参加してくれるようになりました。今では全長817m、105haに及ぶマングローブ林となり、沿岸地域は地元の人々にとって豊かな漁場となっています。この交流訪問にはATINA(オルター・トレード・インドネシア)職員やエコシュリンプ生産者も同行し、地元の人々とマングローブと漁獲高の関係について意見交換を行いました。
 |
 |
|
| パスルアンのマングローブ | マングローブの苗木を手にするムカリムさん |
【3月22日】2日目に開催されたシンポジウムには、エコシュリンプ生産者、ATINA職員、環境NGOや政府の水産局からも参加がありました。ATINAからは、エコシュリンプの生産から加工までの行程の説明、若手生産者のイルル氏からは、自分たちが実践している「粗放養殖」について、そして今直面している問題として環境汚染と生産性について報告がありました。ECOTON(環境NGO)からは、スラバヤを流れるブランタス川の環境保全活動について報告がありました。日本側からの発表は、「野付植樹協議会」からは、消費者や川上の酪農農家と協力して植樹活動を継続した結果、豊かな川の水が戻り漁獲高もあがって後継者には困っていないという魅力的な報告がありました。(消費者団体である生協といっしょに植樹を始めて10年になりますが、その前に浜の母さんたちが漁獲量が落ちていくことに気づき、その原因としてたどりついたのが牧草地開発のために山の木が切られ、さらに牛の糞尿による汚染の問題だったそうです。そこで、豊かな水を戻すために、浜の女性たちが中心となって植林活動が始まったのだそうです。)そして、沖縄の恩納村でのサンゴ植樹とモズク生産の取り組み、最後に「安さのみを求めた消費は環境を破壊し生産システムを破壊することにつながりやすい。分断の経済から協同の経済へ、そして一握りの人に集積される富に対して民衆の経済づくり、すなわち協同組合づくりが重要である」というパルシステム生協連合会の考え方が紹介されました。エコシュリンプ生産者たちも真剣に耳を傾けていました。
【3月23日】舟で川を下りながらエコシュリンプの粗放養殖池を訪問しました。エビの成長行程、池の仕組み、粗放養殖についてATINA担当者から現場で学んだ後は、手づかみ収獲体験をしました。エコシュリンプは元気に勢いよく逃げますので、つかみ取るのはなかなか容易ではありません。実験池で獲れたてのエコシュリンプづくしの昼食をいただいた後は、参加者全員でパスルアンから入手したマングローブ苗の植樹を行いました。 【3月24日】まとめの会では、今回の出会いから有効な交流を続けてお互いにもっと状況をよくしていきましょう、と確認し合いました。
 |
 |
|
| エビ生産者代表のイルルさん | マングローブの苗木を手にするムカリムさん |
(交流事業推進室 幕田)

































