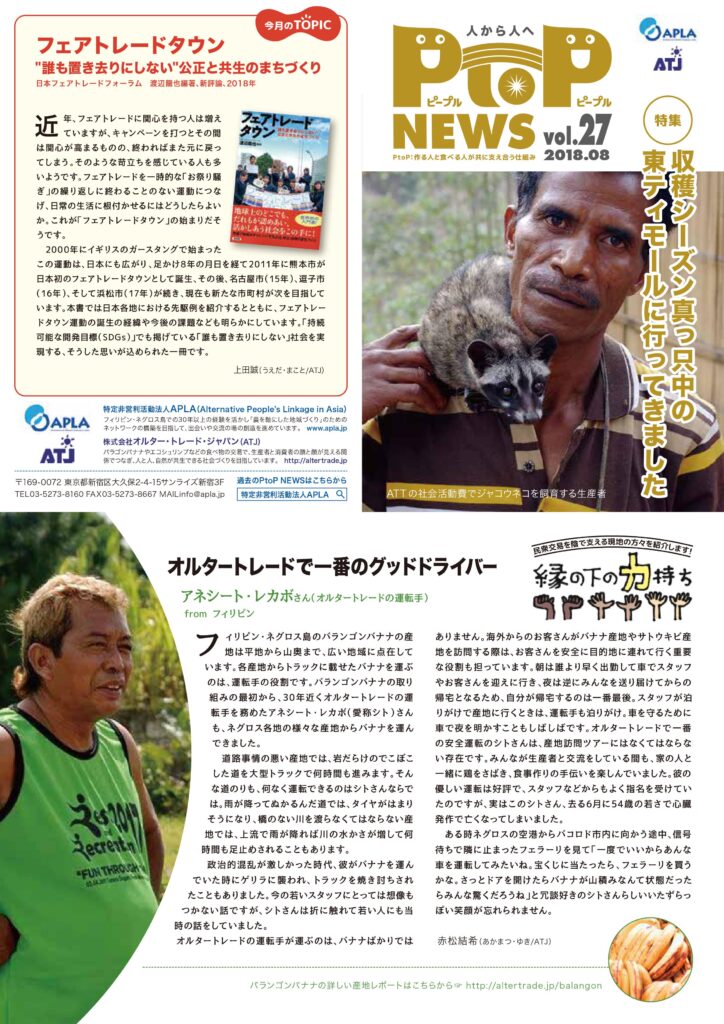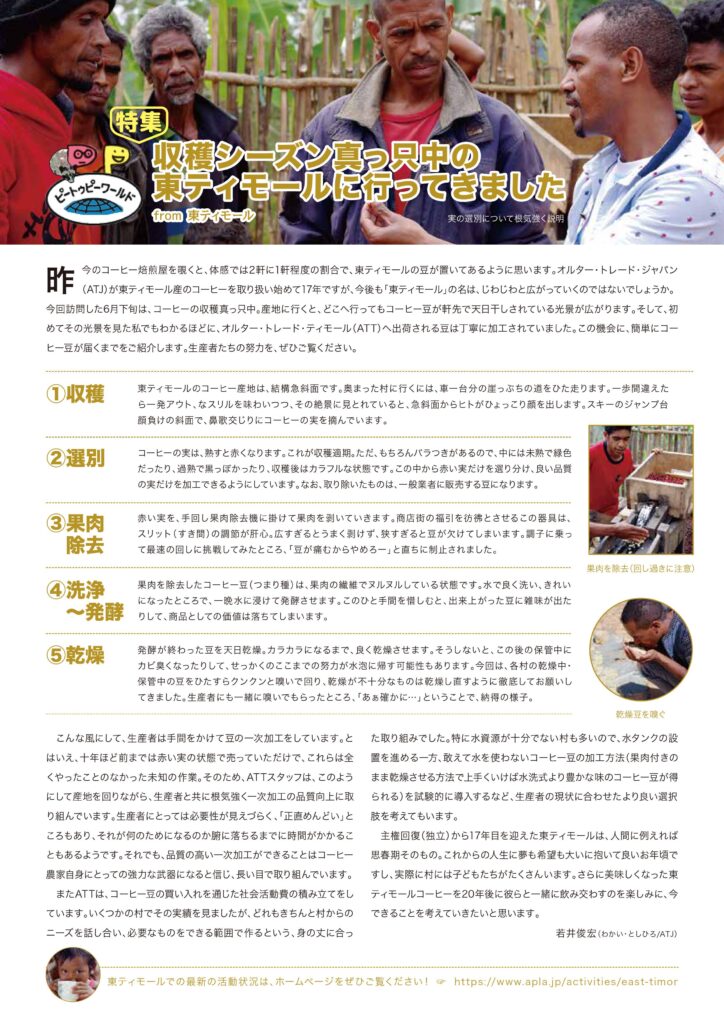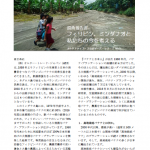月: 2018年8月
パプアからの便り Vol.05 発行/2018年7月25日
カカオ産地のインドネシア・パプア州では、3月から6月にかけてのカカオ収穫ピークが一段落しました。
お陰様で、今年の収穫状況は良く、KAKAO KITA(わたしたちのカカオ社、以下カカオキタ)と一緒に取り組んでいる村々からもたくさんのカカオ豆が集まりました。
これからカカオの小さな花が大きな実になるまで(約6ヵ月)、カカオの木を大切に手入れしていかなければなりません。
特にカカオの花は雨にあたると落ちてしまうことが多いので、花が咲く時期に雨の日が多いとカカオ生産者たちの顔が曇ります。
幸い今年はこの時期、南半球が冬の季節を迎えている影響なのか、雨が少なく比較的乾燥した気候です。たくさんの花が実を結びますように!と期待しています。
さて、今回はカカオキタの貯蓄プログラムについて少しお話させていただきます。
カカオキタはカカオの生産者(パプア先住民族)からカカオ豆を買付けている事業体で、生産者から消費者までそこに関わる人びととの「友情と連帯」を基盤とした切磋琢磨の学び合いを通じて、自然と共生するパプア先住民族の社会と文化を維持・発展させることを事業の目的としています。
このため、ただ単にカカオ豆を買付けることをしていません。何よりも生産者一人一人とのコミュニケーションを大事にし、地域全体が住民たちの力で少しづつ良い方向に向かっていくことに伴走していきたいと思っています。
【カカオを通じた取り組みの理解を深める】
カカオキタではカカオの買付をはじめる前に、対象の村で生産者を集めて説明会を開いています。
説明会では、「カカオキタは単にカカオ豆が欲しくて買付けているわけではない。」ということをまず強調します。
カカオ豆を通じて、遠く日本の人びとと繋がること、友達になること、お互いの違いを尊重し、その違いが力となって関係性が発展していくこと、などをカカオキタ代表のデッキーさんが情熱込めて語りかけます。
「わたしたちはカカオにパプア人の誇りと友情を託しているのだ。良いカカオ豆であるという誇り、そして食べる人を思い農薬や化学肥料を使わない安心・安全のカカオを届ける、という友情だ。」
デッキーさんの話に耳を傾ける人びとの目は輝き、何か新しいこと、素敵なこととして、パプアの人びとの胸に響いていると思います。今までは、現金を得るためだけだったカカオに、新しい意味ができました。
【貯蓄プログラム】
デッキーさんはカカオ事業をはじめる当初から、「パプア人は現金を手にしてもすぐに使って手元に残らない。これでは意味がない。
カカオを売って得たお金の一部を貯金するプログラムを平行して行うことが大事だ。」と言っていました。
貯蓄プログラムをはじめた2015年6月、プログラムの説明会で銀行に貯金するシステムは何やら良くわからないが、デッキーさんが言うように「子供の教育や家族が病気になった時に備えてお金を貯めるのは良いことだ」と思う人が、最初は17名程が口座開設しました。
その後口座開設者はどんどん増えて、2018年6月末時点で口座開設者は10カ村で240名になりました。
カカオキタ貯蓄プログラムとタイアップしているのは1990年代にパプアのNGOがバングラディシュのグラミン銀行から学んで設立した民衆信託銀行です。
小さな民に寄り添う民衆銀行は不備のある身分証明書でも口座開設OK、というところが有難いです。(村では有効な身分証明書を持っていない人も結構多いのです。)
生産者はカカオキタに豆を売るときに貯金したい額をカカオキタに預け、カカオキタが町の民衆銀行で代理で入金します。
カカオキタの買付では多くの人が通帳を手に豆を集荷所に持ってきます。
だいたい、5万ルピア、10万ルピア(日本円で約400円、800円)を貯金に回すという人が多いです。
収穫ピーク時は多くの生産者が貯金するので、カカオキタは豆と一緒にたくさんの通帳も持ち帰ります。
貯蓄プログラムをはじめてから3年目、貯蓄の習慣は生産者の間に根付いてきたようです。
デッキーさんが貯蓄プログラムを考えたその先には、実は、「将来生産者協同組合を立ち上げるときに、生産者自身が出資できる資金を準備すること」、がありました。
この組合を立ち上げる取り組みはまだもう少し先の話になりそうですが、その目標に向けて毎日の活動を大切にしながら着実に一歩づつ、頑張ります!!!
(報告:ATJ 津留歴子)
[box type=”shadow”]【この便りについて】
株式会社オルター・トレード・ジャパンが取り組むインドネシア・パプア州のカカオ民衆交易プロジェクトの、顔の見える関係だからこその産地の情報をお届けします。このカカオ民衆交易では、「パプア人の、パプア人による、パプア人のためのカカオ事業」を現地で推進すると同時に、カカオを作る人、チョコレートを食べる人が相互に学び合い、励まし合いながら人と自然にやさしいチョコレートを一緒に創造していくことを目指しています。
HP:https://altertrade.jp/wp/cacao[/box]
【バナナニュース280号】「甘そうで苦い」 高地栽培バナナの裏側
近年、スーパーの売り場でよく見かける「高地栽培バナナ」。自然な甘みを売りにしたプレミアムバナナとして、高めの値段で販売されています。高地栽培バナナのプランテーション(農園)は、日本で出回るバナナの80%以上を供給しているフィリピン、ミンダナオ島で、2000年代以降、続々と開発されました。
ATJは、その一つ、南コタバト州ティボリ町にある日系企業のプランテーションを視察しました。早朝、上空を軽飛行機が飛び回っています。バナナ栽培にもっともやっかいなシガトカ病を防ぐため、数種類の殺菌剤を散布しているのです。検査等で因果関係が証明されている訳ではありませんが、住民は空中散布による健康被害を訴えています。とくに、子どもに皮膚病や呼吸器系疾患の症状が出ています。自家消費用の野菜を作ることも、家畜を飼うことも難しくなり、飲料水も買わなければならなくなってしまったそうです。
高地栽培バナナのほとんどが日本向けです。住民たちは日本の消費者にこうした現実を知ってもらいたいと口々に話していました。
詳しくは報告書「フィリピン、ミンダナオと私たちの今を考える」をご覧ください。
よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。
[Form id=”15″]
【PtoP NEWS vol.22 特集】パプア クラフトチョコレートの2年目~美味しいチョコレートを自分たちで作る!~from インドネシア・パプア州
パプアのカカオ生産者の「自分たちが育てたカカオから作ったチョコレートを食べたい!」という素朴な願いを実現したのが「パプア クラフトチョコレート」でした。
パプア産カカオ豆をジャワ島にある国立コーヒー・カカオ研究所のチョコレート工房で手作りチョコレートに仕上げ、それを日本とパプアで同時販売しました。
1950年代にパプアを統治していたオランダがカカオの苗木を先住民族に配布しカカオ栽培を始めて以来、カカオ栽培が続けられてきましたが、最終製品のチョコレートがカカオ生産者の元に届くことはありませんでした。
生産者は「カカオは現金収入になる」、という認識だけで半世紀以上カカオ栽培が続けられてきたのでした。
売るだけでは物足りない!
2017年1月からカカオキタ社の拠点であるパプア州ジャヤプラ県で「パプア クラフトチョコレート」の販売を開始するや、評判が口コミで広がり、月に100 ~200個が売れていくという状況が続きました。
積極的な販売活動を展開することが今後の大きな課題ですが、それでも地元の少し高級なスーパーマーケットや空港内のカフェ、観光地で有名な山岳部ワメナのホテルなどからの卸し注文が途絶えることはありません。
「パプア産のカカオから美味しいチョコレートができる」ということに自信を持ったカカオキタのスタッフは、ジャワ島で製造されたチョコレートを売るだけでは物足りなくなり、自分たちでもチョコレートが作れるはずだと考えるようになりました。
こうして始まったのが、原料生産地での一貫製造、森から収穫したカカオ豆を現地で最終製品のチョコレート菓子にしよう、という新たな挑戦です。
小さなお菓子工房が完成!
カカオキタのスタッフがチョコ菓子づくりの指導を受け、2017年9月には、アジア民衆基金(APF)から融資を受けて、小規模なチョコレート製造機械を事務所に設置し、板チョコレート、ブラウニー、チョコレートアイス作りを始めました。
本当に美味しいものができて、今までお菓子を作るなんて考えもしなかったスタッフのジョンを中心に楽しく作業に取り組んでいます。
一番人気はカカオマスを贅沢に練り込んだアイスクリーム。
こちらはジャヤプラ県の中心部にあるパプア農村発展財団(YPMD)事務所内の冷凍庫に在庫を置いて友人を中心に販売を始めたところ、やはり口コミで評判が広がり、毎日コンスタントに50個近くも売れています。
アイスクリームはジャワ島からの移住民が押し車で売りに来るのが今までの風景でした。
合成甘味料や着色料を使ったアイスの味しか知らなかった人びとは、本物のチョコレートアイスの美味しさに目を丸くしています。
値段は少し高めですが、それでも本物の美味しさを知ると安い方に戻ることはできないようです。
YPMD事務所に毎日売りに来ていたアイスクリーム屋さんの姿もいつしか見なくなりました。
自分たちで作ることで大きな変化が!
カカオ豆からお菓子の素材であるカカオマスを作り、それをアイスクリーム、ブラウニー、板チョコレートにする仕事が増えたことはカカオキタスタッフの仕事へのやりがいに大きな変化をもたらしました。
今までは村でカカオ豆を買付け、それを倉庫で発酵や乾燥をさせるだけでしたが、実際にその原料を食べものにすることで「原料の品質」と「最終製品の味」の関係が良くわかってきたのです。
「発酵が浅かったからチョコの風味がいまいちだな」などとブツブツ言いながら作っています。このことは村でカカオ豆を買付けるときに生産者にしっかり発酵させることの意味を力説することにもつながっています。
今は本当に小さな規模での製造ですが、カカオキタ代表のデッキーさんはこんなに楽しいことをカカオキタだけが独占するべきではない、という考えで、もう少し規模の大きなチョコレート工房を作って、多くの生産者がカカオ豆からチョコ菓子まで作れるようになる学びの場にしたいと計画しています。
津留歴子(つる・あきこ/ATJ)
【PtoP NEWS vol.17】ここが知りたい! バナナ
日本人がよく食べる果物ランキングで1位のバナナ。スーパーや百貨店に行くと、さまざまなブランドのバナナが並んでいますが、品種はほとんど選ぶことができません。
今でこそラカタン(スポーツバナナとして売られている)やバナップルといった品種のバナナを見かけることも増えましたが、日本で販売されているほとんどのバナナはキャベンディッシュ。
しかし、バナナは世界で300品種以上あると言われており、フィリピンの市場などでは、色も形もさまざまなバナナが販売されています。
バナナには大きく分けると生食用と料理用があります。
生食用は、キャベンディッシュ以外にも、トゥルダン、ラカタン、赤いバナナのモラードなどがあります。ATJが輸入している”バランゴン”バナナも「バランゴン」という品種名なのです。
フィリピンで一般的に食べられている料理用バナナはサバという品種です。熟すと生で食べることができますが、通常は煮たり焼いたり揚げたりして食べます。
バナナの原産国に行くと、こうしたバナナを食べることができます。皆さんも機会があれば、ぜひお試しください!
黒岩竜太(くろいわりゅうた/ATJ)
パプアからの便り Vol.03 発行/2017年9月1日
カカオの産地、インドネシア・パプア州ジャヤプラは連日摂氏30度を超える熱さで、強い日差しがカカオの木にさんさんと降り注いています。日本の皆さまは如何お過ごしでしょうか? カカオキタのスタッフ、生産者たちはみんな元気にしています!
今年は2月、3月にカカオの森の協働手入れ作業を精力的に行ったことが功を奏してか、3月、4月と生産者はたくさんのカカオ豆を収穫することができました。
こうしたカカオキタが生産者と一緒に取り組む活動が他の村にも知れ渡り、最近はカカオキタのメンバーになりたいという村が増えてきました。
新しくカカオキタの仲間になった村は、パプア州のなかでもオランダが1950年代にカカオ栽培をはじめたグニェム地方にあるスナ村とその近くにあるイブップ村、バンガイ村です。
<スナ村でカカオキタの民衆交易説明会を行いました>
スナ村はオランダがカカオ栽培を1950年代に導入したグニェム地方にあり、村人は昔からカカオ栽培を暮らしの基盤のひとつとしていました。今まではイブ・プール(ジャワ人業者)に、最近はマカッサル人のクスナンさんに売っていたそうです。
スナ村には生産者グループがありメンバーは約50名。このうち30名ほどが集まりました。会合には近隣ブリン村、イブップ村、バンガイ村の生産者も来ていました。
カカオキタ代表デッキーが同じく代表を務めているYPMD(パプア農村発展財団)はスナ村でかつて水道敷設事業を行ったことがあり、会合の挨拶でスナ村の村長は「YPMDの名前はわたしたちの胸にずっと残っていた。」と言い、YPMDの長年の活動が今のカカオ事業に繋がっていることがわかりました。
デッキーは、パプアのカカオ豆から作ったチョコレートが日本で売られていること、ビジネスに慣れていないパプア人を支援してくれる日本の人びとのこと、そして、パプアからはオーガニックで安全な食べ物であるカカオを提供することがパプアのプライドになること、などを得意な歌やユーモアを交え語りかけ、集まった生産者たちは目を輝かせていました。
特に「わたしたちパプア人はインドネシアのなかでは圧倒的にマイノリティーだが、カカオの質はインドネシアを越えて世界で通用する質であることに誇りを持とう!」というところでは皆うれしそうに拍手していました。
<道路拡張工事―木材伐採と自然破壊>
カカオ産地に向かうセンタニ湖から森林地帯に入る道で大工事が進んでいます。
これは内陸部の木材を積みだすコンテナが通れるように道幅を広げているのだそうです。
緑に覆われていた山肌が削られ剥き出しの土が露わになっている横を通過するたびに「これからパプアはどうなるのだろう」という不安が胸に押し寄せます。
(報告:ATJ 津留歴子)
[box type=”shadow”]【この便りについて】 株式会社オルター・トレード・ジャパンが取り組むインドネシア・パプア州のカカオ民衆交易プロジェクトの、顔の見える関係だからこその産地の情報をお届けします。 このカカオの民衆交易では、「パプア人の、パプア人による、パプア人のためのカカオ事業」を現地で推進すると同時に、カカオを作る人、チョコレートを食べる人が相互に学び合い、励まし合いながら人と自然にやさしいチョコレートを一緒に創造していくことを目指します。 HP:https://altertrade.jp/wp/cacao[/box]
【PtoP NEWS vol.20/2017.11】バランゴンバナナを洗浄・箱詰めしているパッカーの皆さん from フィリピン・ネグロス島
バランゴンバナナは収穫された後、パッキングセンター(以下:PC)で洗浄・箱詰されています。現在10ヵ所のPCがあり、1つのPCでは約10人のパッカーが作業をしています。
作業時間は産地によって異なります。たとえば、畑が比較的PCの近くにまとまっているミンダナオ島のツピやレイクセブでは、午前中から作業が始まり、夜には終わります。
畑が点在しているネグロス島などでは、集荷に時間がかかるため、PCでの作業は夕方から始まり、バナナの量が多いと作業が終わるのは翌朝になることもあります。
最初に熟度やサイズなど、バナナが出荷基準を満たしているかどうか確認をします。そして洗浄です。
バランゴンバナナは化学合成農薬を使用せずに育てているので、虫がついていることがあります。
そのため、丁寧に洗浄しなければならないのですが、細かいところは洗いづらく大変です。
パッカーの皆さんは口をそろえて「バナナとバナナの間を洗うのが難しい!」と言います。
洗浄後は、バナナの軸の形を整え、箱詰めするために指定の量になるよう計量をします。
房の大きさが異なるバナナを一定の重さに計量するのは難しく、慣れていないと、何度も房を入れかえて、重量を調整する必要があります。
経験を積んだパッカーは房の大きさで重さの見当がつくので、計量作業もスムーズに進みます。
最後は箱詰め。おそらくこれが一番経験の問われる作業です。多国籍企業のプランテーション・バナナは房の大きさが均一なので、毎回同じように箱入れをすることが可能ですが、バランゴンバナナはそうはいきません。
様々な大きさのバナナを箱詰めしていくのは、まさにパズル。房の大きさを見ながら入れる順番と場所を考えていかないと、全てのバナナを上手に箱詰めすることができません。
パッカーの皆さんには、そんな熟練した技術が必要なのです。PCでの作業は、毎週または隔週で2日程度なので、多くのパッカーは他の仕事もしています。ミンダナオ島のツピでは地域のキリスト教徒とムスリムが一緒に働いており、両者の平和的な関係性構築に貢献しているとも言われています。
このように、バランゴンバナナは生産者以外にも重要な役割を担う人たちがたくさんいます。パッキングセンターで働くパッカーたちは、まさに縁の下の力持ちです。
黒岩竜太(くろいわ・りゅうた/ATJ)
PtoP NEWS vol.27
PDFファイルダウンロードはこちらから→P to P NEWS vol.27