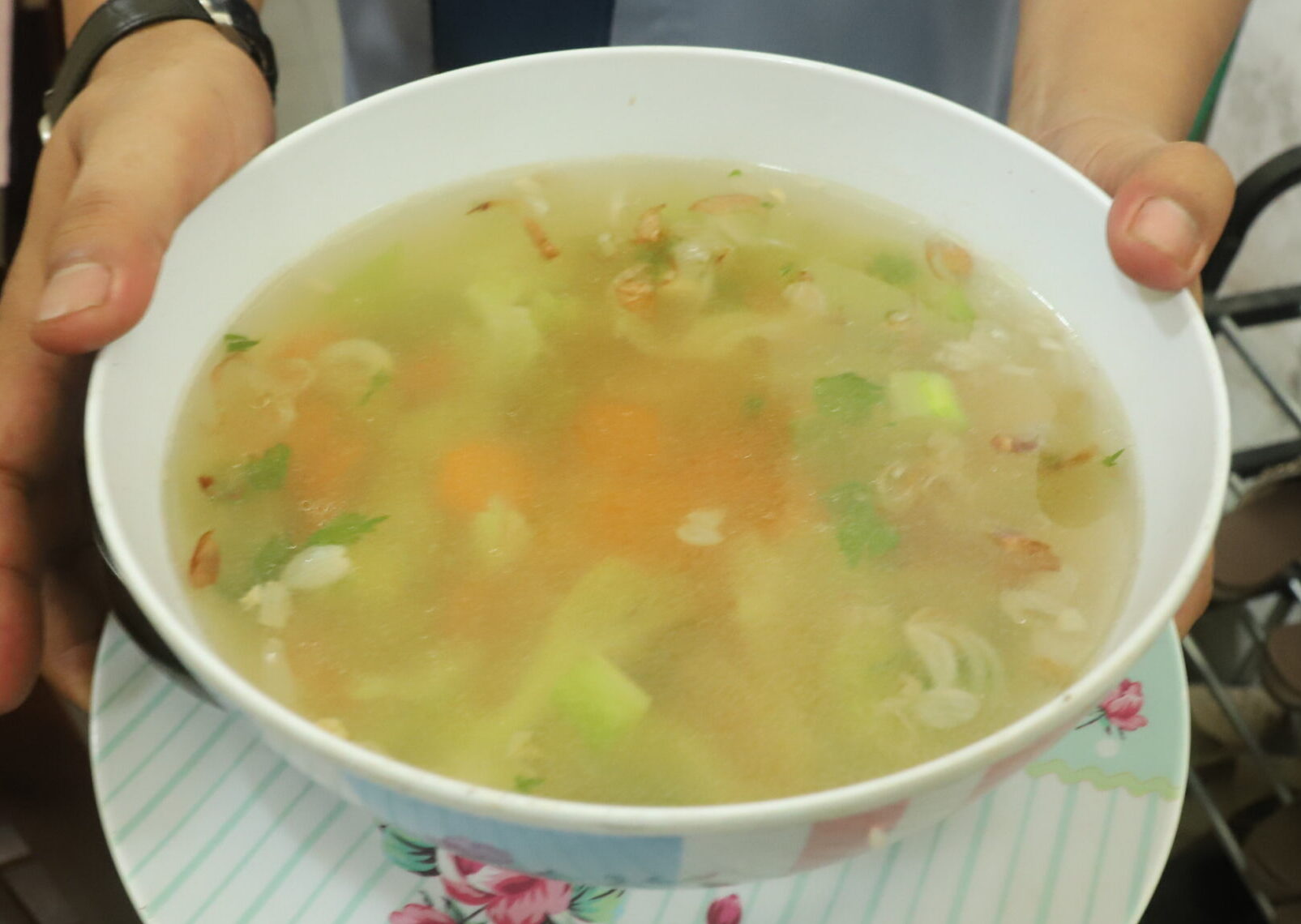エコシュリンプ
Ecoshrimp


生産者の創意工夫の積み重ねと地域の自然の力を活かした「粗放養殖」によって、
健やかに育てられたエビです。
- 生産者は養殖池周辺の環境を守りながら、自然の力を活かした養殖方法(粗放養殖)で育てています。
- 池干しによる養殖池の土づくり、水の入れ替えなど、生産者が手をかけてつくった生育環境で育ちます。
- 稚エビ放流後は、人工飼料をいっさい与えません。養殖池にいるプランクトンなど、自然の餌を食べて育ちます。
- 粗放養殖の養殖密度は1㎡当たり3~4尾程度。大量生産ができる一般的な集約型養殖のおよそ10分の1です。のびのびとした環境で健康的に育っているので、抗生物質を投与する必要がありません。
- 現地法人オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)が、養殖池の定期監査、自社工場で黒変防止剤(酸化防止剤)や保水材を使用せずに製造を行い、生産から加工、輸出まで一貫した管理を行なっています。
エコシュリンプってどんなエビ?
私たちがつくっています

- スヘリさん 東ジャワ州シドアルジョ県の生産者
- 日々養殖池を見回り、エビが病気にかかっていないか、水質が悪化していないか、大雨が降った後は養殖池の塩分濃度が適切かなどを確認しているスヘリさん。
- 「大量生産・一貫管理ができる集約型養殖池に切り替えたとすれば、たしかに一時的にはたくさんエビが獲れて収入が増えるかもしれません。でも、人工の餌をあげたり、薬をたくさん使ったりすることで、やがてその養殖池は使えなくなってしまいます。それに対して、粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられます」と自信を持って言います。

- イスマイルさん 南スラウェシ州ピンラン県の監査人
- エビの養殖について生産者と話し合ったり、エコシュリンプの基準に沿って養殖されているかどうかを確認する監査人。イスマイルさんは2017年からATINA社の監査人として働いており、日々オートバイでピンラン県の養殖池を駆け巡り、生産者と一緒にエコシュリンプの養殖に関わっています。
「エビの収獲量が少ない時は生産者の落胆が伝わり、私も辛い気持ちになります。ですから、自分が関わってきた生産者の養殖がうまくいき、たくさんのエビが収獲できると私もとても嬉しくなります。これからも安心・安全で美味しいエコシュリンプをお届けできるように日々の仕事を頑張りますので、今後もエコシュリンプを食べ続けてくださると嬉しいです。」
▶イスマイルさんへのインタビューはこちらからご覧いただけます。

- ウィナルシさん エコシュリンプ加工場工員
- ウィナルシさんは、2008年からオルター・トレード・インドネシア社(ATINA)で働いており、現在は殻むき部門のリーダーです。加工場ではエビを新鮮なうちに加工しなければいけないので、その日のエビの収獲量によって作業時間が左右されてしまうのですが、殻むき作業を計画通りに進めていくよう作業全体を管理しています。
約200人いる工員さんの多くは女性です。ウィナルシさんには高校3年生の娘と小学校2年生の息子がいます。「家計を助けることが仕事のモチベーション、熱意を持って仕事をしていきたい」と語るウィナルシさん。エコシュリンプのおいしさは、加工場のスタッフたちの頑張りにも支えられています。
▶ウィナルシさんへのインタビューはこちらからご覧いただけます。