投稿者: okubo
脇役にしておくにはもったいない!らっきょう甘酢漬け
マスコバド糖ジンジャーエール
食のギャラリー/エコシュリンプ「ちらし寿司」
【賛同署名のお願い】「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」共同声明
ATJは「パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会」のメンバーとして、パレスチナで活動するNGOとともにガザ地区の恒久的停戦とパレスチナの和平を求める声明を発表し、広く団体・個人の賛同署名を集めています。パレスチナ人の離散を象徴する日である5月15日(ナクバの日)まで署名を募り、内閣総理大臣、外務大臣、及び関係議員へ提出する予定です。
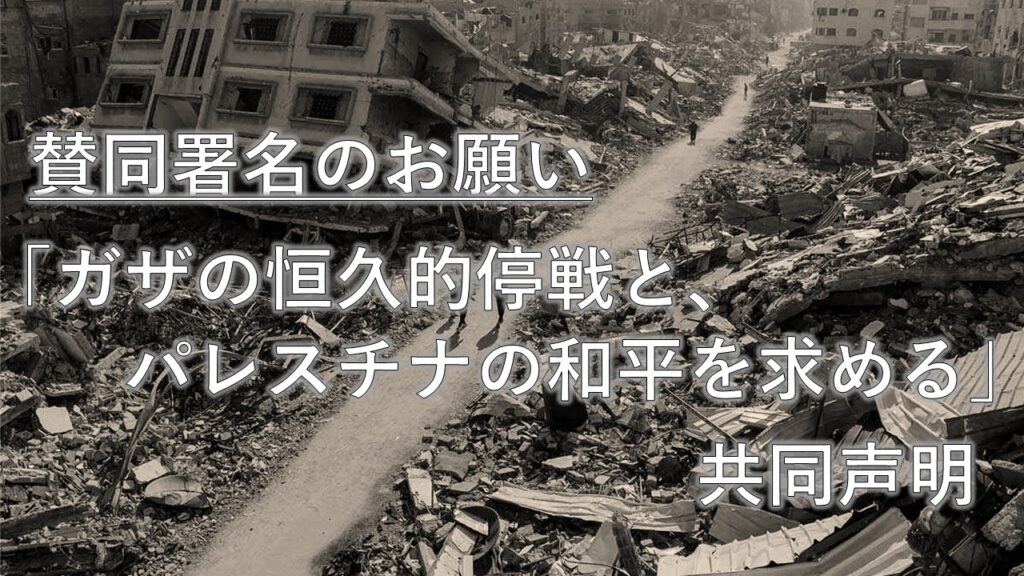
3月24日に行われた「互恵のためのアジア民衆基金(APF)」理事会で、パレスチナ農業開発センター(UAWC)代表でAPF理事でもあるフアッド・アブサイフ氏よりガザ地区及びヨルダン川西岸地区での近況報告がありました。
1月19日に停戦合意が締結されたものの、イスラエル政府は3月2日よりガザ地区を全面封鎖し、そのため多くの人々が飢餓に瀕していること、そして3月18日以降のイスラエル軍の再攻撃によりガザ地区の人びとが置かれた状況は2023年10月に戦争が始まった時よりさらに厳しいと話しています。
「一人の人間として、私たちとともに立ち上がり、即時かつ恒久的な停戦、占領の終結、封鎖の解除を求める声明に賛同してくださるようお願いする次第です。
すべての賛同署名は、沈黙に抗う声です。
すべての賛同署名は、この犯罪を拒否するものです。
すべての賛同署名は、人間性を共有する行為です。
パレスチナが求めているのは、哀れみではなく正義であり、涙ではなく声です。
署名を。情報拡散を。そして立ち上がってください。
安全保障、政治、沈黙の名の下に、今まさに虐殺されている人々のために。」(フアッド氏)
パレスチナ農業復興委員会(PARC)からもメッセージが届きました。
「パレスチナの人々は、76年以上にわたって平和を求めて闘い続けてきました。しかし、この困難な時期にあって、私たちは、パレスチナ人の政治的・人道的権利、そして自己決定権を支持し、行動してくださる世界中の友人たちの支援によってこそ、平和を実現できると確信しています。」
オリーブオイルを通じて繋がっているパレスチナのパートナーのこの切実な訴えを受けて、パレスチナの人々が人権、尊厳が守られた暮らしを一刻も早く送れるよう、皆様からの賛同署名を切にお願いする次第です。また、情報拡散にもご協力賜りますようお願い致します。
賛同署名を呼び掛けるチラシを用意しました。どうぞご活用ください。
バランゴンバナナのキャラメルアイス
【バナナニュース362号】パイナップルを羨むことなかれ
~バナナ担当者小島の出張見聞録⑩(不定期で掲載します)~
皆さんはパイナップルやバナナがどのように実るか描けるだろうか。
私はフィリピンでパイナップルを見て驚いた。パイナップルは、アロエのような葉を放射状に広げ、その中から茎を伸ばし、膝上ほどの高さに実を付ける。

一方で、バナナは地下の根茎から葉の一部が重なって幹のように見える偽茎を伸ばし、2~3mの高さに約30㎏の房を実らせる。そのため、強風で倒れることが頻発する。現地で倒れたバナナを見て「なぜ、重い房をそんなに高い所に実らせるのか。倒れるではないか」と思うことが多かったので、パイナップルを見て、これはお利巧な植物なのかもしれないと思った。
しかし、バナナにはバナナの事情があって、上に伸びているはずだ。高い場所でバナナの大きな青々しい葉を広げればより効率的に光合成ができるし、倒れても本来バナナにはタネがあったのだから、繁殖に関しては問題はなかったはずである。ついつい自分の都合で考えてしまったことを反省しつつも、やはりバナナの倒伏被害を目にすると、生産者を気の毒に思うので、バナナにはなんとか強風に耐えてほしいと願ってしまうのが正直なところだ。


バナナが実っているとその重さで余計に倒伏しやすくなる。
パイナップルを勝手に羨んだが、パイナップルにはパイナップルの事情があり、パイナップルも人間も、それぞれがそれぞれに振り回されながら生きているのだろう。

<バナナ担当者小島が産地で見聞きしてきたことを連載中!>
食のギャラリー/塩「蒸し野菜」
卵かけごはんにオリーブオイル!
カツオのオリーブオイル漬け
オリーブオイルが味の決め手!ヨーグルトディップ(ザジキ)
食のギャラリー/バナナ「バランゴンバナナケーキ」
食のギャラリー/バナナ「ひんやり黒糖寒天」
食のギャラリー/マスコバド糖「オートミール」
ジェノサイドの手段としての飢餓 ―ガザ地区の飢餓についてUAWCからの声明
パレスチナ農業開発センター(UAWC)は、ガザ地区にて深刻化する飢餓について緊急の注意喚起をします。この大惨事は、イスラエルによるジェノサイド攻撃によって意図的に引き起こされたものです。2025年3月2日以降、イスラエル占領軍は、ガザ地区へのすべての食料および人道支援の搬入を阻止しています。4月7日(月)、イスラエルの財務相ベザレル・スモトリッチは「小麦の一粒さえもガザ地区に入れさせない」と発言し、ガザ地区に飢餓を強要するというイスラエルの方針を再確認しました。これは政策の失敗ではなく、大量の飢餓を計画的に進める入念に計画されたキャンペーンです。

今日、ガザ地区の人々は意図的に飢えさせられています。
パレスチナNGOネットワーク(PNGO)は、ガザ地区を公式に「飢餓地域」と宣言し、国際社会にも同様の認定を求め、即時の介入を呼びかけています。PNGOは、特に子ども、女性、高齢者への壊滅的な影響を警告しており、イスラエルが食料・医薬品・燃料・安全な水の搬入を故意に拒否していると非難しています。ガザ地区は飢餓の末期段階に入り、34万5千人が「総合的食料安全保障レベル分類(IPC)の第5段階(大惨事/飢餓)※にあり、住民の91%が危機レベルかそれ以上の食料不安に直面しています。これは国際社会の沈黙による計画的なジェノサイド行為です。
パレスチナ保健省によれば、6万人以上の子どもたちが急性栄養失調により回復不能な健康被害のリスクにさらされています。生後6ヶ月未満の乳児は、安全な水、粉ミルクや栄養支援を受けられず、感染症や乳児死亡のリスクを高める手段に頼らざるを得ない状況です。人道支援団体は、栄養検査の実施能力が30%低下し、離乳食などすぐに食べられる栄養食品もほぼ尽き、わずか400人の子どもしか支援を受けていないと報告しています。栄養支援のための施設の少なくとも15%が爆撃や避難の影響で閉鎖に追い込まれています。
イスラエルによる完全封鎖により、水へのアクセスも危機的状況にあります。
100万人以上(うち40万人が子ども)は、1日1人あたり6リットル(停戦中は16リットル)しか水を得られておらず、燃料供給が再開されなければ4リットル未満にまで減る恐れがあります。公衆衛生施設の崩壊とともに、水が原因による感染症が急増しています。イスラエルが管理するガザ地区への3本の水道管のうち、2本が切られました。1本は1月以降から止まっています。唯一稼働中の水道管はハンユニス地域に限定されており、イスラエル占領軍は他の水道管の修理を認めていません。南部最大の海水淡水化施設は電力不足により出力が85%削減されています。
病院は、容赦ない空爆による負傷者対応に追われるなか、衛生用品がまったくないため感染症予防もできない状況です。
250以上の医療施設が、ガザ地区の外で留められている医薬品、石鹸、消毒剤、滅菌用品などの必須物資を待っています。患者も医療従事者も完全に無防備な状態です。
ガザ地区の農業セクターは、計画的に破壊されました。
UAWCと食料安全保障に関わるパートナー団体は、食料生産の破綻をすべての分野で確認しています。農地の爆撃、ビニールハウスの破壊、灌漑システムの寸断、家畜は殺され、漁業は完全に麻痺しています。家畜は治療されずに感染症で死亡しており、農民は空爆や不発弾の脅威で農地に近づくことができません。漁船は壊れたまま放置され、漁師は海に出ると襲撃や逮捕の対象となります。結果として、ガザ地区は自給自足の能力を完全に失っています。
環境の崩壊も危機を加速させています。
イスラエルによるインフラの破壊は、土壌の汚染、大気の汚染、廃棄物処理システムの崩壊をもたらしました。5000万トン以上の瓦礫と人間の遺体が未回収のままであり、こうした状況下で有害物質へ曝されることが日常的になっています。世代を超えて大切にされてきたオリーブ畑や農地も壊滅しました。
これは人道的危機ではなく、“構造的な抹殺”です。
イスラエル占領軍は、包囲したガザ地区の住民の意志を打ち砕き、未来を消し去るために飢餓を兵器として使い続けています。ガザ地区の飢餓は偶発的ではありません。これは意図的なジェノサイド政策の結果であり、アメリカ、ドイツ、その他の共犯国によって支えられています。
国際刑事裁判所ローマ規程第8条第2項(b)(xxv)によれば、「戦争の手段として意図的に民間人の飢餓を引き起こすこと」は「戦争犯罪」に該当します。
UAWCは、パレスチナの食料主権が正義と解放の闘いと不可分であることを強調します。私たちはPNGOとともに、国際社会に対し、懸念の表明を超えて、飢餓の根本原因、すなわちイスラエルの軍事占領、入植型植民地主義、継続する封鎖と正面から向き合うよう呼びかけます。そのためには、以下が必要です:
- 即時かつ妨げのない人道的支援の搬入
- ガザ封鎖の解除
- 国際法に基づくイスラエルの責任追及
<国際刑事裁判所(ICC)および国際司法裁判所(ICJ)において)> - パレスチナ主導によるガザ地区の食料システム再建への支援
再確認します。この飢餓は、物流の問題ではありません。これは「戦争犯罪」です。
そして、それは「今すぐ終わらせなければなりません」。
※食料不安を計測する世界標準「総合的食料安全保障レベル分類(IPC)」の定義による第5段階が壊滅的飢餓、第4段階が緊急事態
食のギャラリー/コーヒー「ハンドドリップ」
食のギャラリー/エコシュリンプ「えび豆腐ナゲット ~ハニーマスタードソース~」
「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」記者会見が行われました。

2025年3月28日、「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」記者会見が、日本プレスセンタービル9F(東京都千代田区)にて行われました。この記者会見は、3月30日の「パレスチナ土地の日」を前に、ATJやAPLAの他、パレスチナで活動するNGOで立ち上げた「パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会」によって開催され、複数の団体が連携して3月10日に発出した共同声明の発表と、パレスチナの現状が伝えられました。
当日の報告は以下の通りです。
●趣旨説明、停戦前後の現地状況の説明:ピースウィンズ・ジャパン
●ガザ地区の状況:日本国際ボランティアセンター(JVC)、パルシック
●ヨルダン川西岸地区の状況:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、APLA
●「ガザの危機 国際法の観点から即時停戦を求める」:ヒューマンライツ・ナウ 伊藤和子氏
APLAの野川事務局長は、パレスチナ農業開発センター(UAWC)が制作したヨルダン渓谷で入植者によって400頭の羊が強奪された農民の取材動画を上映して、西岸地区で頻発する放牧地での入植者による組織的暴力について報告しました。
会見全体の様子はこちらからご覧いただけます。
記者会見の様子は以下のメディアで報告されました(掲載日順)。
○3月28日(金) NHK
パレスチナで支援活動の日本のNPOなど 恒久的な停戦の実現訴え
○3月28日(金) 朝日新聞
ガザの恒久的停戦を求める声明 パレスチナで支援の日本のNGO発表
○3月28日(金) 8bit News
ガザの恒久的停戦とパレスチナ全体の和平を!支援団体が訴える現地の今
○3月29日(土) 日本農業新聞
オリーブ園攻撃、羊の盗難… 戦禍のパレスチナ農業 日本の農家へ「心寄せて」 支援団体が緊急会見
○3月29日(土) 朝日新聞 朝刊・WEB
NGO「ガザ恒久的停戦を」
○4月2日(水) レイバーネット
ガザの恒久的停戦とパレスチナの和平を求める声明
○4月3日(木)日本農業新聞
[論説]パレスチナの戦火 和平へ思い連帯しよう
○4月6日(日) 東京新聞
「私たちの苦しみ想像できますか」ガザで悲痛の叫び イスラエル軍需企業に投資する日本政府が考えるべきこと
なお、声明は5月15日(ナクバの日)まで団体・個人の賛同を募り、内閣総理大臣、外務大臣、及び関係議員へ提出する予定です。引き続き、賛同・情報拡散にご協力を宜しくお願い致します。
【バナナニュース361号】 絵本『バナナのらんとごん』のご紹介🍌
2024年12月に絵本『バナナのらんとごん』を出版しました。(株)オルター・トレード・ジャパンの姉妹団体であるNPO法人APLAが、クラウドファンディングで多くの方に応援いただき制作した絵本で、和歌山県にある「らくだ舎出帆室」と共同出版しました。

この絵本は、バランゴンバナナのらんとごんの姉弟が日本の消費者に届くまでの旅を通して、身近な食べ物の背景を知ることができるものです。バランゴンバナナがどのような場所でどのように育てられているのかを紹介するために、産地の様子や生産者の工夫などを盛り込みました。
絵本後半ではフードロス問題も扱っています。日本に届いたバナナが、実に届くような深いキズが皮にあるなどの理由で規格外に分別されているという内容を入れ、ふだん手にしているバナナの、なかなか見ることのない裏側も知ってもらいたいと思いました。

資料ページが4ページもあります。本編では描ききれなかった内容や産地の写真を入れており、授業やワークショップに役立つ内容になっています。

「傷があってもおいしく食べられる」「捨てるのはもったいない」と規格外のバナナへの思いや、「イラストが鮮やか」「大人が読んでも学びがある」と絵本自体の感想も寄せられています。SDGsを達成するために大切な要素も散りばめられているので、読み聞かせ会などにご活用いただけるとうれしいです。
APLA福島
食のギャラリー/マスコバド糖「寄せ豆腐」
「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」共同声明および記者会見(3/24追記)
パレスチナのオリーブオイルの産地、ヨルダン川西岸地区ではオリーブオイルの出荷団体であるパレスチナ農業開発センター(UAWC)からの緊急報告(緊急報告1、緊急報告2)にあったように1月19日に発効したガザ地区での停戦合意以降、イスラエル軍による軍事攻撃が激化しています。
ATJは「パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会」のメンバーとして、パレスチナで活動するNGOとともにガザ地区の恒久的停戦とパレスチナの和平を求める声明を発表し、ガザ地区およびヨルダン川西岸地区の状況を広く知らせるために3月28日に記者会見を行います。
3/24追記:
こういった思いをお持ちのみなさまにもご参加いただけるよう、この声明に対する賛同を広く募ることにしました。賛同は個人、団体両方あります。何卒、ご賛同をお願い致します。また、情報拡散にもご協力賜りますようにお願い致します。
こちらの声明は、パレスチナ人の離散を象徴する日である5月15日(ナクバの日)まで、賛同(団体及び個人)を募り、内閣総理大臣、外務大臣、及び関係議員へ提出する予定です。
声明の内容は下記をご覧ください。なお、3月28日記者会見で、それまでに集まった賛同団体の名前と個人の賛同者数を発表する予定です。
「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」声明 賛同フォーム
https://forms.gle/t17dM91wey8uZ2PJ7
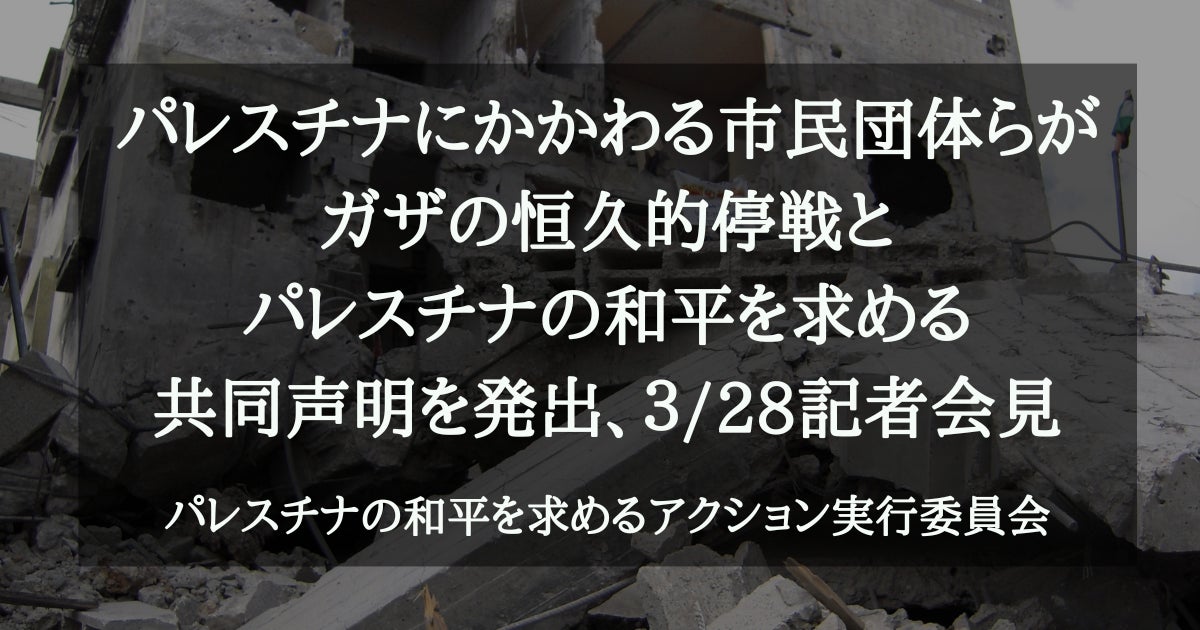
「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」声明
2025年3月10日
パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会
パレスチナ・ガザ地区における未曾有の人道危機は、少なくとも4万8千人[1]の尊い命を奪い、2025年1月19日、三段階あるとされる第一段階の停戦が実現しました。しかし、ようやく結ばれた停戦は決して恒久的なものではなく、人質の解放、大規模攻撃の再開、さらに食料や医療品など人々の命に係わる物資の搬入や送電までが取引の材料にされた状態で、今にも崩れ去ろうとしています。無辜の市民の命が一部の権力者によって操られていることに、強い憤りを覚えます。
第一段階目が実行された16日後から交渉される予定だった停戦の第二段階目では、ガザの恒久的停戦と、イスラエル人の人質およびパレスチナ人被収容者の双方の解放に加え、イスラエル軍のガザからの完全撤退が含まれることとなっていました[2]。しかし、それらは未だ実行されていません。そうした中、3月4日、イスラエル政府はガザの実効支配勢力に対し、人質の解放が達成されていないことを理由にガザへの攻撃再開を宣言し、米国政府はそれを支持しています。
パレスチナの平和と人道支援に関わり続けてきた日本の団体として、私たちはここに改めて人質・被収容者の無条件の解放と、イスラエル軍のガザからの完全撤退、そして恒久的停戦を実現するよう、両者に強く訴えます。
また、ガザでの停戦後、ヨルダン川西岸地区でのイスラエル軍や入植者による攻撃が激化している事実も看過することができません。西岸地区の北部、特にジェニン難民キャンプやトゥルカレムを中心に4万人以上もの市民が住む家を追われ、帰る場所を失っています。2024年1月から2025年1月の僅か1年間で、102人の子どもを含む555人がヨルダン川西岸地区で犠牲となりました[3]。攻撃の影響を最も受けるのは一般の市民です。私たちは、このような状況に晒されている人々の命と人権が守られるよう、日本政府が国際社会の一員として、ガザの恒久的停戦と共に、パレスチナ全体の和平の実現に向けて、あらゆる外交努力とアクションを引き続き行うよう、強く求めます。
[1] Reported impact snapshot | Gaza Strip (4 March 2025)
[2] How does the ceasefire deal between Israel and Hamas work?, BBC, 3 Mar 2025
[3] West Bank Monthly Snapshot – Casualties, Property Damage and Displacement | January 2025
私たちは、上記の声明の発表と、ガザ地区およびヨルダン川西岸地区の状況を広く知らせるために、記者会見を行います。
イスラエル建国とパレスチナ難民の発生から今年で77年目を迎えます。イスラエルによる1976年の大規模な土地接収に対する抗議で死者・負傷者が出た事件を悼み、各地でアクションが行われる3月30日の「土地の日」を前に、今一度パレスチナに思いを寄せ、パレスチナの人々がイスラエルの人々と対等な権利を享受し、自由に暮らせるために何ができるかを考える機会になればと思います。
「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」記者会見
◎日時:2025年3月28日(金)10:30‐11:45 (受付開始10:15)
◎場所:日本プレスセンタービル9F 会見場 東京都千代田区内幸町2-2-
◎プログラム
・趣旨説明、ガザ停戦を巡る動き
・ガザ地区の状況(現地で活動するNGOからの報告)
・ヨルダン川西岸地区の状況と現地からのメッセージ
・質疑応答
・写真撮影
主催:パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会
(実行委員会構成団体、五十音順)
特定非営利活動法人APLA
特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク
株式会社オルター・トレード・ジャパン
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター
公益財団法人 日本YWCA
特定非営利活動法人パルシック
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
ピースボート
この声明文に関する連絡先
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター(JVC)
〒110-8605 東京都台東区上野 5-22-1 東鈴ビル 4F
info@ngo-jvc.net / 03-3834-2388(担当:酒寄、今井)


